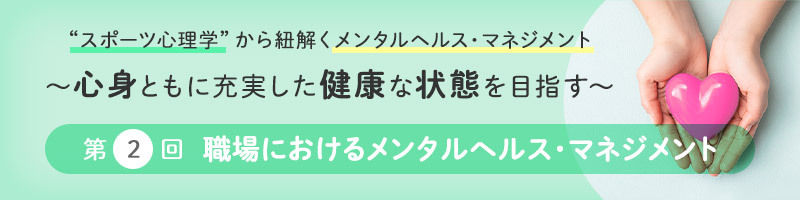特別企画
ヘルシーエイジング(健康長寿)のためには、健康的な食事や生活習慣だけでなく、メンタルヘルスを維持することも大切です。そこで、自分自身のメンタルヘルスのコントロール方法や、メンタルヘルスを維持するために必要な周囲のサポートのあり方などについて、専修大学 スポーツ研究所 教授 佐藤 雅幸 先生に、ご専門の“スポーツ心理学”の見地からお話を伺いました。
今回は、職場や社会生活において、仕事のパフォーマンスや生活等に影響が生じるくらいストレスを感じている方も多いことから、その対処法やメンタルの保ち方についてのアドバイスをいただきました。

健康保険の傷病手当金の申請理由のうち、最も多いのがメンタルヘルス不調等(※協会けんぽが毎年実施している「現金給付受給者状況調査報告」より)という現状を踏まえ、仕事や職業生活において、不安や悩み、ストレスを感じることがいかにメンタルに大きなダメージを与えているか、その影響は職場や社会において深刻な問題になっています。
自分がやっている仕事について、評価されていないと感じる事などそれぞれ職場の悩みはあると思います。そういう時には、もう一つ評価される場やストレスのない場所・環境を作って“ダブルスタンダード”で考えるようにするのも精神的にはとても良いことに思います。自分を守る場所、良い意味の逃げ道・環境を確保することは、最大の防御にもなります。ストレスがたまる職場があっても、別の場所に行けば回避できたり癒されたりする場所があれば大丈夫という事が出来ればいいですね。
企業も職場において、ストレスチェック制度を導入する (「労働衛生安全法」で従業員50人以上の事業所では毎年1回ストレスチェックが義務づけられている)など試みて対応していますよね。
参考:厚生労働省「ストレスチェック制度導入マニュアル」
・不調が見受けられた場合の安全配慮義務に則った対応について
・相談への対応 (話の聴き方、情報提供および助言の方法、声がけのタイミング)
・心の健康問題をもつ復職者への支援の方法
などが記載されていますので、活用して頂けたらと思います。
こういうチェックを行う事も良いと思うのですが、1つ気を付けてもらいたいことは、チェックをした後のフィードバックのスピードです。チェックを受けた後なるべく早くその結果を知らせ、アドバイスをすることが大事で、早ければ早い程良いため、できるだけ早いタイミングでのフィードバックを心掛けてもらいたいと思います。
健診結果も同じで、かなり時間が経って忘れた頃に戻ってくることも多いですが、機を逃しては折角の効果が期待できません。
「失敗をしたくない」「怒られたくない」という考えから、現実に向き合うのが困難に思われる方もいるようですが
“GRIT(グリット)”という言葉を知っていますか?「やり抜く力」、「粘る力」を表す言葉で、 “G=Guts(ガッツ:度胸)、R=Resilience(レジリエンス:回復力・適応力)、I=Initiative(イニシアチブ:自発性)、T=Tenacity(執念、粘り強さ)”でこれらの頭文字をとってGRITと言います。
これらは目標達成のために大切な要素です。何かを足し遂げた人の中で、努力無しに達成した人はいません。
例えば金メダルを獲得した人でも、その後にどん底を経験した人もいます。それを乗り越えた人たちはどんなメンタルを持っているのか調査した結果、このGRITの要素が高かったという結果が出ましたが、これらは元々あるものではなく、実は“鍛えられて育つもの”だということがわかっています。
特に「回復力」でいうと、以前の状態に戻るのではなく、立ち上がって回復していく過程で前よりも良い状態になるということがあります。
「失敗したくない」という感情は、実は人間の進化の過程でDNAに埋め込まれたもので、当たり前の考えでもあります。例えば大昔の時代では”失敗=死”を意味し、狩猟で失敗すると獲物に逆襲されて死ぬこともあるので“失敗は絶対に許されない”という観念がありました。だから人は失敗しちゃいけない、失敗を避けるようにする考えが自然に備わっています。
アスリートが苦難を乗り越える時に、「大丈夫」と自身に言い聞かせることで、ネガティブな思考をポジティブに変換します。こういった心理スキルを仕事や日常生活でも積極的に活用してほしいものです。
世代別のメンタルヘルスケアについてお尋ねします。生きてきた環境や考え方、世代によっても捉え方が違うと思いますが、世代によってメンタルヘルスを保つための対処法に違いがあるのでしょうか?
私は今、自分がどの時点を生きているのかを認識してもらうために、*「人生時計」の話をします。
94年にスウェーデンで元メンタルトレーニング学会会長のラーシュ・エリック・ウーネストールのセミナーで「あなたの人生時計は今何歳ですか?」というエクソサイズを受けました。多摩大学教授の久恒啓一先生の著書『図で考える人は仕事ができる』にも書かれていますが、自分の人生を1日24時間の時計に置き換える事で、自分の今の人生の立ち位置を客観的に知るというものです。
人生を始めたばかりでしかない学生が「もうダメだ」と早まった考えをすることがありますが、判断するには尚早だということを知ってもらうため、「人生時計」について解説しています。
我々もよく「もう歳だから」と言いがちですが、思い込みで判断せず、自分の年齢を1日に例え、客観的な物差しで理解するために生み出された発想です。もし、残り時間が少ない事を認識したら、その時間を無駄なく有効に使う方法を考えることで有効に使うことができるはずです。
*人生時計:
人生100年時代と言われてもピンとこないが、自分の人生を1日24時間に置き換え、今が何時にあたるのかを知る事で、自分の立ち位置、人生あとどれだけ残っているのかを実感し、有意義な時間の使い方や生き方を見直すための例え

人生時計の係数の求め方<例>
現在の平均寿命(男性 81.05 女性 87.09)÷24時間= 係数(男性3.38、女性3.63)
年齢÷係数=人生の時刻
例;68歳÷3.38(係数)=20.12時
“マインドフルネス”はご存じですか?スポーツ選手や企業の経営者が心身の健康のために採用したことで一般的にも知られるようになりました。呼吸法や瞑想を取り入れ、心身のリラクセーションからスタートしますが、マインドフルネスの興味深い考え方を紹介したいと思います。まずは本人、あなた自身が幸せでありますように、苦しみ・迷い・恐れから解消できますようにと願います。そして次に身内、例えば家内や子どもが幸せでありますように、痛みから解放されますようにと願います。次に親、親族、友達、と自身に近い人達から次々に幸せを願っていきます。さらに、対象を広げていき、同僚、得意先、知人・・へと、遠い存在の人に対しても幸せを願います。最後に嫌いな相手や憎んでいる相手に対しても、幸せを願います。そうすることで、物の見方、考え方に変化が生じて心が広くなり安定していくことが分かってきました。
また、マインドフルネスに「四股踏み」「足の踏みしめ」エクササイズがあります。地面を強く踏むことで大地のエネルギーを取り入れることができるという考えです。この動作は、オリンピックなどでレスリングの選手や柔道の選手が試合前に行っているのを目にした方もいらっしゃるのではないでしょうか。アスリートが採用していることは良く知られていますが、実は、難病や不治の病を治療しているドクターやナースも積極的に採用しているようです。医療の現場において、大きなストレスや苦悩を抱えている患者と向き合う重圧は、計り知れないものだと思います。この重圧に向かい負けないために、ドクターやナースは、足を踏みしめる動作をしながら、自分は何のために医者になったのか、医療従事者としてどうあるべきか、など考えるうちに勇気湧き出てきてポジティブな思考に変わっていくのだそうです。
大地を踏みしめる動作をしながら心と体を整えて澄んだ精神状態にすることが出来れば、気持ちが楽になりポジティブで健康的な思考になるはずです。是非とも試してみてもらえたらと思います。

監修
専修大学 スポーツ研究所 教授
佐藤 雅幸 (さとう まさゆき)先生
専修大学 教授(スポーツ心理学)
専修大学スポーツ研究所所長を経て現在は顧問。
82年日本体育大学大学院体育学科研究科修士課程修了。
同大学女子テニス部を創部し監督を務め、92年は全日本大学王座優勝を果たした。現在は同女子テニス部統括。94年には、長期在外研究員としてカロリンスカ研究所・ストックホルム体育大学に留学。現在、松岡修造氏が主宰する「修造チャレンジ」におけるメンタルサポートの責任者として活躍中。『起きあがりことば』(朝日出版)、『人はなぜ、負けパターンにはまるのか』(ダイヤモンド社)など著書多数。